※本記事にはプロモーションが含まれています。
子どもの習い事選びで迷わないために!親が知っておくべき基本
子どもの習い事は、単なるスキルアップの場ではなく、社会性や協調性、そして何よりも「自己肯定感」を育む大切な機会です。「何を習わせたらいいのだろう?」「いつから始めるべき?」といった疑問や不安を持つ保護者の方も多いのではないでしょうか。
この章では、習い事選びを成功させるために、親がまず考えるべき「目的」と「子どもの特性の見極め方」について解説します。
習い事を始める「目的」を明確にする
習い事を始める前に、まずは「なぜその習い事をさせたいのか」という目的を明確にすることが重要です。目的が明確であれば、途中で迷った時や、子どもが壁にぶつかった時のサポートもしやすくなります。
主な目的の例
- 身体的な成長:運動能力の向上、体力づくり、健康維持など(例:水泳、体操)
- 知的好奇心の育成:学習習慣の確立、新しい知識の習得、論理的思考力の養成など(例:英語、プログラミング、公文)
- 情操教育・表現力:感性や創造性の育成、自己表現の場の提供など(例:ピアノ、絵画、ダンス)
- 社会性の育成:集団行動でのルールやマナーを学ぶ、協調性を育むなど(例:チームスポーツ、集団レッスン)
親の「将来のために」という期待も大切ですが、子どもの「今」の成長に必要なものは何か、という視点を持つことが、子どもの意欲を引き出す鍵となります。
子どもの「興味」と「適性」を見極める
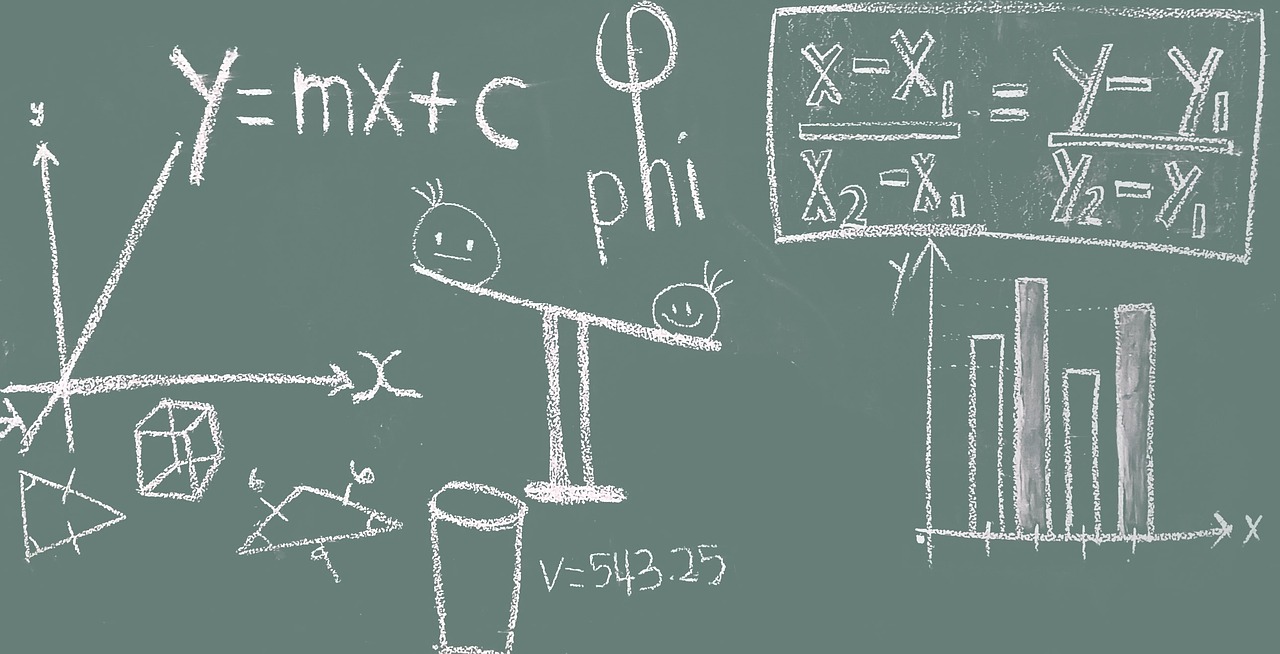
習い事が長続きし、子どもにとって有意義な時間となるかどうかは、「子ども自身の興味」に深く左右されます。親が「これが良いはず」と決めつけるのではなく、子どもの日々の行動を観察しましょう。
観察のポイント
- 自発的な行動:いつも何かを描いている、音楽に合わせて自然と体が動いている、パズルやブロック遊びに集中しているなど、自ら楽しんでいることは何か?
- 人との関わり方:一人で集中する方が好きか、友達とワイワイ活動するのが好きか?(集団か個別かの判断材料)
- 持続性:飽きっぽいか、一つのことに長く熱中できるタイプか?(習い事のペースや種類を選ぶ参考)
体験レッスンや短期教室を利用して、実際に子どもがその活動に触れてみる機会を作ることも非常に有効です。親の目から見て適性があっても、子どもが楽しめなければ、習い事は長続きしません。
人気の習い事ジャンル別解説:運動系と学習系のメリット・デメリット
子どもの習い事には、大きく分けて「運動系」「学習・知育系」「芸術・文化系」があります。それぞれが子どもの成長に与える影響は異なり、メリットと注意すべきデメリットも存在します。ここでは、特に人気の高い運動系と学習系に焦点を当てて解説します。
運動系習い事:体力向上と精神的な成長
水泳、体操、サッカー、ダンスなどの運動系の習い事は、身体的な発達はもちろん、精神的な成長にも大きなメリットをもたらします。
水泳・体操:基礎体力と怪我の予防
- メリット:水泳は全身運動であり、心肺機能の向上に優れています。幼少期から始めやすく、年齢を問わず続けられる点も魅力です。体操は体の柔軟性やバランス感覚、調整能力といった運動の基礎を養います。
- デメリット:特に専門的な競技に進むと、練習時間が増え、他の活動との両立が難しくなることがあります。また、水泳は冬場の送迎時の体調管理に注意が必要です。
チームスポーツ(サッカー・野球):社会性と協調性

- メリット:チームメイトとの協力や役割分担を通じて、社会性や協調性、コミュニケーション能力が養われます。勝利を目指す過程で、困難に立ち向かう精神力も育まれます。
- デメリット:試合や練習の送迎負担が大きくなりがちです。また、レギュラー争いなど、人間関係のトラブルや挫折を経験する可能性もありますが、これも成長の糧となり得ます。
学習・知育系習い事:学力アップと将来のスキル
英語、プログラミング、そろばん、学習塾などの学習・知育系の習い事は、学力向上や将来のキャリアにつながるスキルの習得を目的とします。
英語・英会話:コミュニケーション能力と異文化理解
- メリット:早期から英語に触れることで、抵抗なく自然な形で言語を習得しやすくなります。将来のグローバル社会でのコミュニケーション能力の土台を築けます。
- デメリット:週に一度のレッスンだけでは定着しにくく、家庭でのフォローアップや継続的なインプットが必要です。アウトプットの場が少ないと、学習が停滞しやすい傾向があります。
プログラミング:論理的思考力と問題解決能力
- メリット:物事を順序立てて考える論理的思考力や、失敗から解決策を見つけ出す問題解決能力が養われます。デジタルネイティブ世代として、新しい技術への適応力も高まります。
- デメリット:教材やPCなどの初期費用がかかる場合があります。また、子どもの興味が湧かないと、ただの作業になってしまい、楽しさを見失うこともあります。
いずれの習い事も、子どもにとって負担になりすぎないよう、親がスケジュールや費用のバランスを考慮することが重要です。
習い事を継続させるための環境づくりと親の関わり方
習い事を始めたものの、数ヶ月で「行きたくない」と言い出す子どもは少なくありません。子どもの才能を伸ばし、習い事を通じて成長を実感してもらうためには、親がどのように関わり、家庭内でどのような環境を整えるかが非常に重要になります。
「親の期待」と「子どもの現実」のバランス
親が習い事に過度な期待をかけることは、子どもにとって大きなプレッシャーになることがあります。習い事の本来の目的は、その道のプロになることよりも、**「非認知能力」**を育むことにあります。非認知能力とは、目標に向かって頑張る力、感情をコントロールする力、他の人と協調する力などのことです。
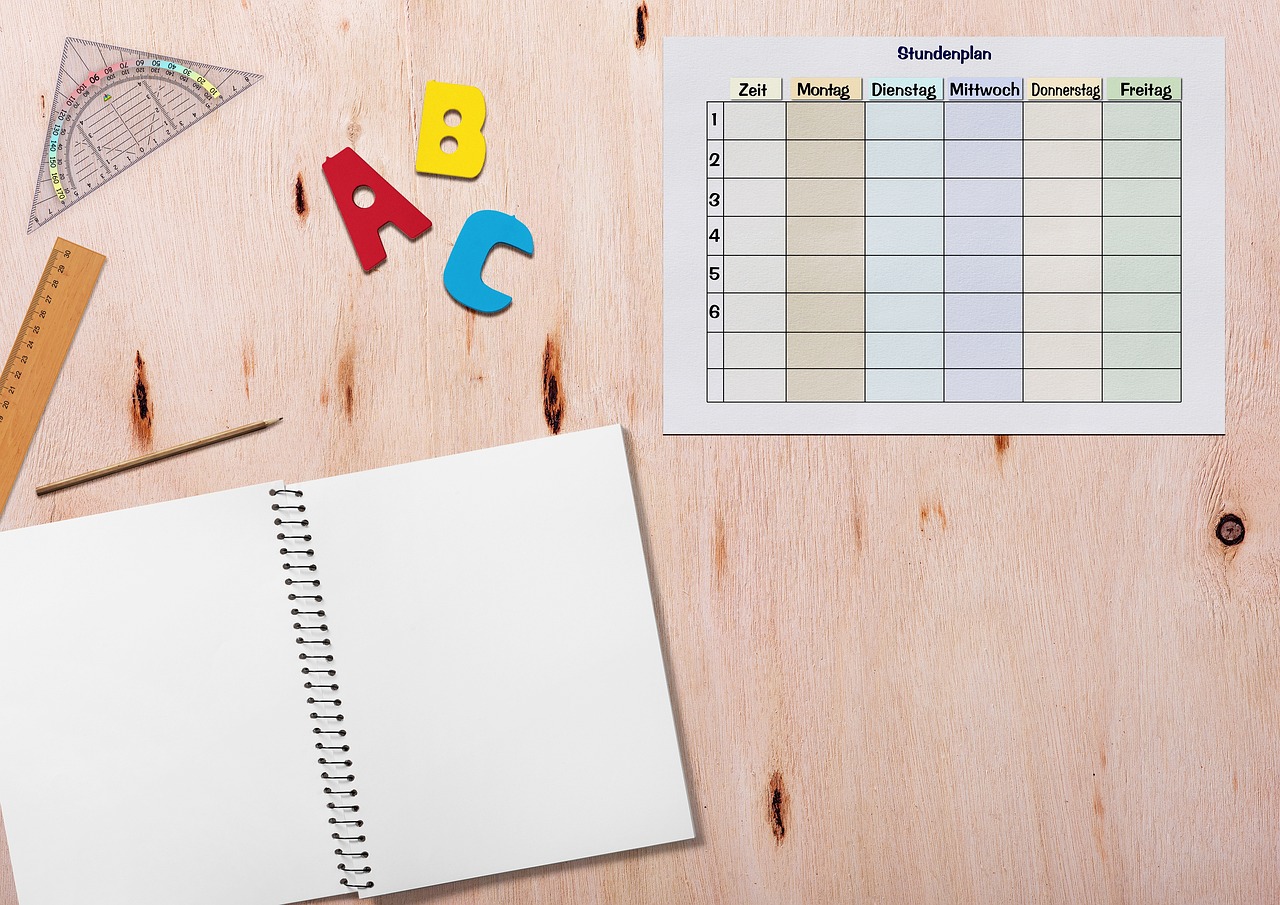
継続をサポートする親の関わり方
- 結果ではなく過程を褒める:上手にできた時だけでなく、「毎日練習を続けたこと」「難しくても諦めずに取り組んだこと」といった努力の過程を具体的に褒めましょう。これが自己肯定感につながります。
- ネガティブな言葉を避ける:他の子と比較したり、「どうしてできないの」と責めたりする言葉は、子どもの意欲を奪います。「次はどうしたら良くなるかな?」と一緒に考える姿勢が大切です。
- 休む日を作る:習い事が増えすぎると、子ども自身の自由な時間が奪われ、かえってストレスになります。習い事のスケジュールと、家族で過ごす時間や休息の日のバランスをしっかり確保しましょう。
子どもが本当に辞めたいと言い出したときも、すぐに受け入れるのではなく、辞めたい理由をじっくり聞き、本人が納得できる形で次のステップを考えることが重要です。
習い事と家庭学習の両立をサポートする環境
特に小学校高学年以降になると、習い事と学校の宿題、家庭学習の両立が課題になってきます。効率的に両立させるには、生活全体を見直す必要があります。
時間管理と「見える化」
一日のスケジュールを家族全員で**「見える化」**しましょう。冷蔵庫などに週間スケジュール表を貼り、習い事の時間、帰宅後の自由時間、宿題の時間を色分けして書き込みます。これにより、子ども自身が「この時間までにこれを終わらせよう」と、時間管理の意識を持つことができます。
また、習い事の準備(持ち物チェックや着替えなど)を子ども自身にさせる習慣をつけることで、自立心も育まれます。親はあくまでサポート役に徹しましょう。
習い事の成果はすぐに現れないと知る
習い事の効果は、すぐに目に見える形で現れるものではありません。特に情操教育や思考力を養う習い事は、数年単位の継続によって、子どもの人格や能力の土台を築くものです。
保護者は長期的な視点を持ち、焦らず、子どもがそれぞれの習い事を通じて得られる**「喜び」と「成長」**を見守り続けましょう。子どもの「やりたい」という気持ちを大切にし、適切なサポートを続けることが、習い事を成功に導く最も確実な道です。


